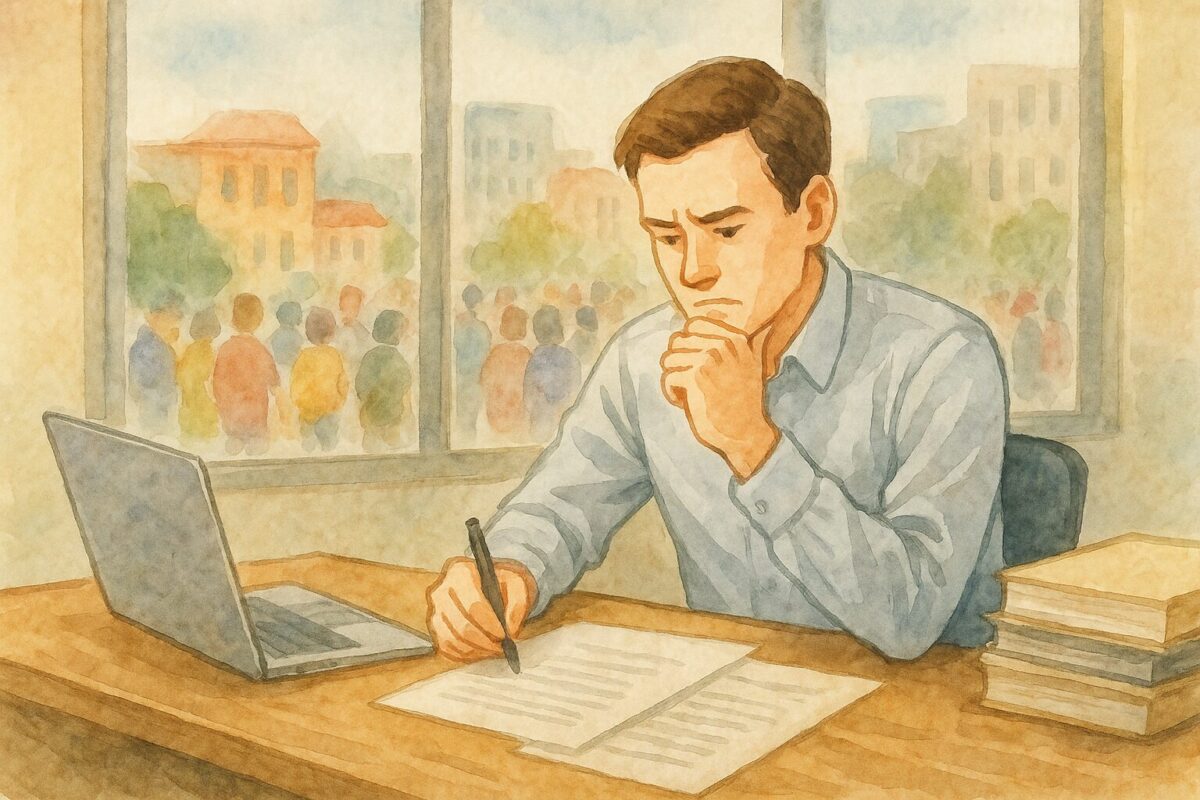
「働きがいって、なんでしょう」
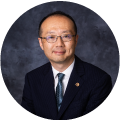 弁護士:島田 直行
投稿日:2025.05.03
弁護士:島田 直行
投稿日:2025.05.03
本日は連休の後半の初日ということで、事務所の周りにも観光客の方々がたくさんいらっしゃいました。やはり人の動きが増えると、街が少し明るく見えるような気がします。活気があるというのは、それだけで良いものですね。
私はこのような連休の時こそ、たまっていた仕事を一気に片付けようと意気込むタイプです。普段の業務の中では、ついつい後回しにしてしまうような細かい作業がどうしても残ってしまいがちですから、こういった機会を利用してまとめて処理してしまおうと毎回思うのです。
しかしながら、実際はなかなか思い通りにはいきません。時間がたっぷりあるからこそ、かえって集中できなかったり、ついネットを眺めてしまったりと、思いがけない方向に時間が流れてしまうことも少なくありません。気づけば、「また連休が終わってしまったなぁ」と毎年同じような反省をしている自分がいます。
そんな中、今日は「働きがい」ということについて少し考える機会がありました。最近では、若い世代にとって「働きがいのある職場」が重要だとよく言われます。実際、企業の採用活動においても、「働きがい」をどう提示するかが大きなテーマになっているようです。
もちろん、働く人がやりがいや充実感を感じられる職場を目指すことは、とても大切な視点だと思います。ただ一方で、私は「働きがい」という概念そのものがとても主観的で、掴みどころのないものだとも感じています。
例えば、「働きがいって何ですか?」と尋ねたとしたら、人によって答えはまったく異なるでしょう。ある人にとっては収入かもしれませんし、ある人にとっては社会貢献や達成感かもしれません。それぞれの価値観や経験に左右される以上、「これが働きがいです」と一言で定義することは、なかなか難しいように思います。
私自身の感覚としては、働きがいとは「後から積み上がってくるもの」ではないかと思っています。つまり、初めから「これはやりがいのある仕事だ!」と確信して始める人は少なく、実際に手を動かして失敗したり、小さな成功を重ねたりしながら、少しずつ自分の中に働きがいのような感覚が芽生えていくのではないでしょうか。
ですので、「社員に働きがいを感じさせる職場づくり」といったとき、与えるべきは「働きがいそのもの」ではなく、「達成感を少しずつ積み上げられる道筋」ではないかと思います。
特に中小企業では、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)として、実際の業務を通じて人を育てることが多いかと思いますが、何をどの順番で任せていくのか、どのように達成感を感じてもらうかを丁寧に設計することが大切です。
単に「簡単なことからやってもらおう」と考えるだけでは、その仕事が本当に簡単なのか、初心者にとって適切なのかが抜け落ちてしまうことがあります。また、簡単すぎる仕事ばかりでは、本人の成長実感が得られず、モチベーションも続きません。
自分の実力よりも少し背伸びをしたタスクに挑戦し、それを乗り越えたときに感じられる「ちょっと頑張った達成感」こそが、働きがいの根っこなのではないか。そんなふうに感じた一日でした。
CONTACT
お困りごとは、島田法律事務所で
解決しませんか?
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
オンライン相談をZoomでも対応しています。
083-250-7881
[9:00〜17:30(土日祝日除く)]


![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)
![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)