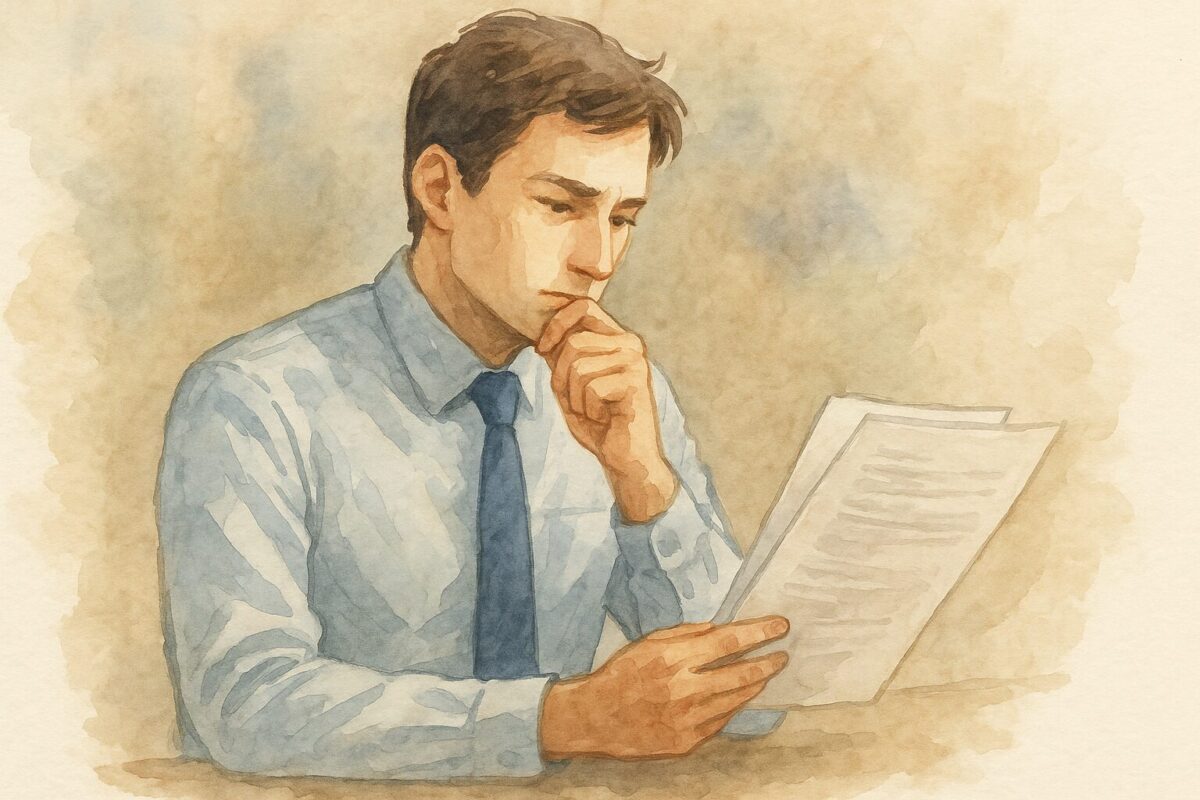
「仮説は壊すために立てるもの」──その勇気について考える
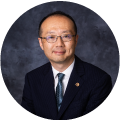 弁護士:島田 直行
投稿日:2025.05.07
弁護士:島田 直行
投稿日:2025.05.07
連休が明けて、事務所も再始動しました。毎年のことですが、連休明けというのは、休み中に滞っていた案件や連絡が一斉に押し寄せてくるタイミングです。朝からフル回転で対応していると、夕方にはもうヘトヘト。きっと、同じような状況の方も多いのではないでしょうか。
さて、今日は「仮説を立てること」について書いてみたいと思います。これは、仕事の効率化にも深く関わるテーマです。
弁護士の仕事においても、仮説を立てるという作業は不可欠です。事件を解決するには、調べた事実や手元の証拠をもとに、一つのストーリー(仮説)を描くことから始まります。その仮説に基づいて、主張の方向性を決めたり、今後の戦略を練ったりするわけです。
ただし、仮説というのは、最初から正しいことの方がむしろ稀です。調査を進めていくうちに、最初に立てた仮説と食い違う事実や証拠が見つかることもあります。そういうときに、「じゃあ仮説を立てる意味なんてないじゃないか」と思ってしまいそうになりますが、実はその逆なのです。
仮説があるからこそ、それと矛盾する事実が現れたときに、「なぜ違うのか?」という視点が生まれます。その違いこそが、問題解決の重要なヒントになるのです。仮説がなければ、それぞれの証拠や事実はただバラバラに存在しているだけで、結びつきが見えにくくなってしまいます。
ですから、私は事務所の職員に対しても、仮説を持って仕事に取り組むようにと伝えています。ただし、ここで気をつけたいのが「仮説に縛られすぎない」ということです。
人は一度立てた仮説に愛着を持ってしまうものです。そのため、仮説と食い違う事実が出てきたときに、それを無理に仮説に当てはめようとしてしまうことがあります。でも、それをやってしまうと、実際の姿とは異なるストーリーが出来上がってしまい、最終的には混乱を招きかねません。
また、私たちはどうしても、自分に都合の良い情報だけを拾ってしまう傾向があります。仮説があると、なおさらそうなってしまうのです。自分の立てた仮説に合わない情報は、つい無視してしまいがちになります。
だからこそ大切なのは、「仮説を壊す勇気」を持ち続けることです。せっかく時間をかけて考えた結論を、自ら否定するというのは、なかなかできることではありません。ある意味、自分で自分の考えを破壊するような作業です。しかし、それをしなければ、物事の本質にはたどり着けないのだと思います。
人はつい、「ここまでやったんだから、この方向でうまくいってほしい」と思ってしまうものです。でも、そこを一度立ち止まって見直せるかどうか。自分の思い込みを手放せるかどうか。それこそが、経験の差なのではないかと私は感じています。
仮説を立てること、そしてそれを壊す勇気を持つこと。この二つは、どんな仕事でも通じる普遍的な力なのかもしれませんね。
CONTACT
お困りごとは、島田法律事務所で
解決しませんか?
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
オンライン相談をZoomでも対応しています。
083-250-7881
[9:00〜17:30(土日祝日除く)]


![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)
![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)